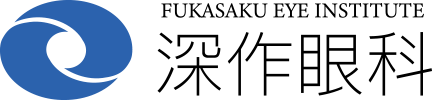網膜剥離の前兆は?症状の見分け方や検査方法を解説

網膜剥離は目が見えなくなってしまう病気だと思っていませんか?
早期発見・早期治療が重要な網膜剥離は、前兆に気づき眼科を受診すれば、視力障害を回避できる可能性が高まります。
この記事では、網膜剥離の前兆症状やどのような検査をするのかなどを、詳しく解説します。
網膜剥離に不安を抱えている方や、治療について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
網膜剥離はどんな病気?

網膜は眼球の一番奥にすき間なく張り付いている、0.1〜0.4mmほどの薄い膜状の組織です。
外部から入った光が焦点を結ぶ部位で、カメラに例えるとフィルムの役割を担っています。
人の目にとって重要な組織であり、「物を見る」ために必要不可欠です。
網膜剥離は、網膜がなんらかの原因により浮き上がったり、引っ張られたりして、剥がれてしまう病気です。
網膜剥離とは
網膜は光を感知して伝える神経網膜と、それを支える土台としての網膜色素上皮で構成されています。
2つの組織は接着が弱く、神経網膜が網膜色素上皮から剥がれてしまうと網膜剥離の状態になります。
神経網膜は視細胞から作られ映像を脳に伝える役割を担っていますが、その神経網膜へ栄養を届けるのが網膜色素上皮です。
網膜剥離が起こると、十分な栄養や酸素が供給されず視細胞の機能が低下し、剥離した部分の映像情報が上手く届かなくなり、視野の欠損につながります。
網膜剥離の原因
網膜剥離の原因は、以下のようなものが挙げられます。
- 加齢
- 強度近視
- 外傷によるもの
- 他の疾患によるもの など
これらの要因により網膜に孔が開く「網膜裂孔」が起こったり、網膜の下に液体化した硝子体が流れ込んで浮き上がったりして、網膜剥離が起こります。
加齢による網膜剥離は50代以上で発症することが多いですが、強度近視や外傷、他の疾患による網膜剥離は若年層でも起こるため、注意が必要です。
網膜剥離の種類
網膜剥離には種類があり、原因によって分類されます。
裂孔原性(れっこうげんせい)網膜剥離は一般的に多い網膜剥離で、網膜に孔や裂け目などの網膜裂孔ができることで、孔から目の水分が網膜の下に入り込み、網膜が剥がれてしまうのが原因です。
加齢によるものの他、若年性の場合は強度近視や外傷、アトピー性皮膚炎が原因になる傾向があります。
非裂孔原性網膜剥離は、滲出(しんしゅつ)性と牽引(けんいん)性に分かれていて、孔が原因ではない網膜剥離です。
滲出性網膜剥離とは、眼球の奥にある脈絡膜と網膜の間に滲出液が溜まり、網膜が浮き上がってしまうものです。
ぶどう膜炎や目の腫瘍などの目の疾患だけでなく、妊娠中毒症でも起こる可能性があります。
一方牽引性網膜剥離は、不足した血流を補うために発生した新生血管や増殖組織により、網膜が引っ張られて剥がれる網膜剥離の種類です。
増殖糖尿病網膜症や、網膜静脈閉塞症などが原因で起こります。
非裂孔原性網膜剥離は、原因となる疾患を治療するのが重要です。
また、ストレスが原因で生じる中心性漿液性脈絡網膜症(ちゅうしんせいしょうえきせいみゃくらくもうまくしょう)は、自然治癒するケースもありますが、再発や長期化の可能性もある種類です。
網膜剥離の前兆は?

網膜剥離には、前兆となる症状があります。
一時的ではなく、症状が続くのが特徴であるため、見え方が気になる方は眼科を受診して検査を受けましょう。
飛蚊症
飛蚊症(ひぶんしょう)とは、目の前に虫や黒い点、ごみのようなものが飛んでいるように見える症状です。
加齢によって硝子体がゲル状から液体状に変化していくと共に硝子体の膜が剥がれる後部硝子体剥離が起こります。
液化した硝子体が目の中を動くことで、濁りが見え方に影響して飛蚊症の症状が現れます。
突然目の前に虫のようなものが飛んでいるように見えて、一時的ではなく消えない、または増えていく場合は、網膜剥離の前兆としての飛蚊症の可能性が高いため、すぐに眼科医に相談しましょう。
光視症
光視症とは、暗い場所で起こりやすく、光がない環境でも目の前に点滅している光や稲妻が走ったような光を感じる症状です。
硝子体が網膜から剥がれるときに刺激があり、それを光と認識することで光視症が起こります。
この症状が続く場合は後部硝子体剥離や網膜裂孔が生じている可能性が高く、網膜剥離につながるため、眼科を受診しましょう。
視野の欠け
視野の欠け(視野欠損)は、視界の一部にカーテンがかかったように、そこだけが見えなくなる症状です。
網膜剥離が進行すると見られ、孔の位置や大きさにより網膜剥離の進行速度も異なりますが、視神経が集まる網膜の中心である黄斑に剥離が近づくほど、視野に影響が出てきます。
剥離の場所に対応した視野欠損が起こるため、上側の網膜剥離があると下側の視野が暗くなります。
視力の低下
網膜剥離が進行して黄斑に近づくと、視力にも影響します。
黄斑が完全に剥がれてしまうと、治療をしても視力の回復が望めなかったり、失明してしまったりするケースも考えられます。
メガネの度数を変えても視力の改善がないときは、網膜剥離がかなり進行している可能性があるため、すぐに眼科を受診しましょう。
生理的飛蚊症とは

網膜剥離の心配があるものと異なり、生理的飛蚊症は自然な現象の場合が多く、様子を見ることが多い症状です。
生理的飛蚊症は網膜裂孔がなく、主に加齢による硝子体の変化が原因です。
60代以降は生理的飛蚊症が起こりやすいですが、今すぐ網膜剥離につながるわけではないため、様子を見る場合が多いでしょう。
ただし、今後の進行度によっては後部硝子体剥離が進み網膜剥離になる可能性はあるため、定期的に眼科検診を受けて経過観察が必要です。
黒い点やもやが増えた、視力が急激に落ちたなどを感じた場合は、網膜剥離が起こっているかもしれないと考えて、すぐに眼科を受診してください。
網膜剥離の検査

網膜剥離を診断するための検査は、早期発見のために非常に重要です。
クリニックによって項目は異なりますが、以下のようなものがあります。
眼底検査
眼底検査とは、目の中の血管を直接観察して血管の状態や網膜、視神経など、目の奥の状態を確認できる、網膜剥離の診断に大切な検査です。
一般的に、瞳孔を広げる目薬(散瞳剤)を使用して眼底鏡で瞳孔から光を入れる方法で検査をします。
なお、散瞳剤は瞳孔を開くために30~40分ほど待つ必要があり、検査後はまぶしく感じたり、ピントが合いにくくなったりします。
このため、検査後しばらくの時間は歩行の不便さや文字が読めない、車の運転は数時間行えないなどの制限があります。
検査後すぐに運転をする必要がある方は、眼底検査で散瞳剤を使用するかを事前に確認しておきましょう。
超音波による画像診断(エコー)
通常の眼底検査を行い、硝子体出血で眼内が見えない場合は、超音波検査を行い眼底を確認します。
網膜剥離の範囲や硝子体の状態を画像で診断する検査です。
超音波検査は眼底検査の補助的役割のため、出血がなければ行わないケースもあります。
OCT検査
OCT検査とは、光干渉断層計による眼底三次元画像解析です。
網膜や視神経の断層画像を撮影し、異常を詳細に把握することで、網膜剥離の早期発見に役立ちます。
網膜剥離だけでなく、緑内障や糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症など、他の目疾患の早期発見にもつながるため、眼科検診でOCT検査が含まれているかを確認しておくといいでしょう。
視野検査
視野検査は、見えない部分があるかを調べる検査です。
網膜剥離では必ずしも行うわけではありませんが、視野検査によって進行度を診断する必要がある場合は行うこともあります。
ものを見るときは通常両目で見ていて、どちらかの視野に欠けがあっても正常な目が補っているため、視野欠損に気づきにくく、自覚症状がない方も多いのです。
視野検査では片目ずつ検査を行って異常があるかを判定することで、左右の目それぞれの視野を確認します。
網膜剥離の治療

網膜剥離の治療は、症状や進行度により異なりますが、レーザー治療と手術があります。
ここでは、それぞれの治療について詳しく解説します。
レーザー治療
レーザー治療を行うのは、網膜裂孔・円孔のみで網膜が剥がれていない場合です。
網膜光凝固術で周辺部を固めて、網膜剥離を防ぐ、または今以上に進行しないように予防します。
ただし、裂孔の大きさや硝子体の牽引程度により、予防効果が弱く適用が難しいケースもあります。
レーザー治療は時間がかからず、入院せずに外来で処置できます。
硝子体手術
硝子体手術は、眼球に3〜4つの穴を開けて、内部から治療する方法です。
主に硝子体出血があったり、裂孔が大きい・深いところにあったりする場合に行われます。
抜き出した硝子体の代わりに特殊な眼科用ガスを注入して、網膜を内側から元の位置に戻す手術です。
網膜裂孔は手術中に凝固しますが、剥がれた網膜が眼球の奥に固定されるまでは、うつ伏せ姿勢を保つ必要があるケースもあります。
ガスは時間経過で自然に吸収されますが、術後の回復には個人差があり、約1週間は医師の指示による体位制限があるかもしれないと考えておきましょう。
強膜内陥術
強膜内陥術(バックリング)は、外側から網膜剥離を治療する方法です。
眼球の外側にシリコンスポンジやバックルを巻いて眼球をへこませて、網膜光凝固や熱凝固、冷凍凝固などで網膜裂孔を凝固させて塞ぎます。
網膜下に水分が溜まっている場合は、針で外に排出することもあります。
ガスの注入を行うこともあり、網膜剥離の状態によりますが、うつ伏せ体勢が適している症状もあるため、この場合は体位制限が必要です。
なお、症状の重さや網膜の状態によって、硝子体手術やレーザー治療など、他の治療を組み合わせるケースもあります。
網膜剥離を放置するとどうなる?

網膜剥離は、早期発見して早期治療を行うのが重要な病気です。
前兆に気づいてすぐに眼科を受診したり、定期的な眼科検診で早期発見したりするのが望ましいですが、違和感があるのに放置したらどうなるのでしょうか。
ここでは、網膜剥離を放置した場合に起こり得ることについて、詳しく解説します。
自然治癒は難しい
網膜剥離は自然治癒は難しいため、放置すると徐々に剥離が進行します。
網膜が剥がれ始めても痛みを感じないため、前兆に気づかないと病気の発見が遅れるかもしれません。
飛蚊症や光視症、視野欠損などの前兆を感じたら、すぐに眼科を受診してください。
網膜剥離になっている時間が長ければ長いほど、元の視力を取り戻すのは難しくなります。
失明に至る可能性がある
網膜の中心にある、視神経が密集する黄斑部まで剥離が進行すると、急激に視力が低下して、失明に至る可能性があります。
黄斑は文字を判別する組織でもあり、機能しなくなると視力に影響を及ぼします。
網膜剥離が黄斑にまで及んでいる場合、手術をしても思うように視力の回復ができないケースもあるかもしれません。
視野や視力に違和感があっても放置していると、黄斑部が剥がれて1~2週間で失明することもあるため、注意が必要です。
治療の必要性
網膜剥離は、早期治療をすれば失明を予防する効果が期待できる病気です。
放置しても自然治癒するわけではない以上、失明を防ぐためには治療が必要です。
加齢や強度近視が原因の場合は再発の可能性もありますが、すぐに視力を失うわけではありません。
手術で網膜剥離を治療した後も、再剥離の兆候を見逃さないように、眼科医と相談しながら経過観察を続けましょう。
まとめ
網膜剥離の前兆は、飛蚊症や光視症、視野欠損、視力の低下が挙げられます。
痛みがないため、前兆に自分で気づくのが網膜剥離を発見する方法のひとつです。
見え方の違和感が継続的にあったり、悪化したりする場合は、網膜剥離が進行しているサインかもしれません。
また、視力に不安がない方は眼科に通うことがないかもしれませんが、40~50代になったら定期的な眼科検診を受けて目の状態を把握するのがおすすめです。
外傷や他の疾患による網膜剥離のリスクがある方は、経過観察も含めて半年~1年に1回の眼科検診を受けましょう。
深作眼科は硝子体手術を始めとする多数の手術に対する、豊富な実績と多くの経験をもつ眼科専門病院です。
重症の硝子体手術にも対応できる技術と、広角観察システム「BIOM」などの設備を導入して、「最高の視力を生涯守る」ために患者様のサポートをさせていただきます。
網膜剥離の前兆がある方、手術について詳しく知りたい方は、深作眼科へご相談ください。